2020年5月「安否確認」その3
その1へ<-その2<-その3
さすがプロユースの DENON DL-103 は正常に動いた。それどころか
2020年現在も販売を続けているようだ。違っているのは、デンオンを今はデノン
と発音するらしい。これにはちょっと抵抗あるが・・・。
そしてイコライザーアンプも現役バリバリてあることも分かった。私の身の回りの
いろいろな物が、時の流れで価値を失ったり、使用不能になったりしたため、ちょっ
と心配性になっていたのかもしれない。落ち着いて考えると、アンプ作製に使用した
パーツは、高信頼の物を多く使い、1/4W型で済むところをわざわざ1W型抵抗を
用いたり、コンデンサーの耐圧も高めの物を使用した余裕のある仕様だ。少し警戒感
を緩め、残りのアンプのテストを行った。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
UX-45 シングルアンプ 状態:異状無し(ガリオームの難あり)
 回路構成概略
初段 UY-76
2段 UZ-42 三極管接続
出力段 UX-45 シングル(交流点火・固定バイアス)
OPT TANGO FW20S
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管以外を外し、真空管ソケットで測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター及びフィラメント電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
BIAS調節ツマミを回して 45 のプレート電流を35mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
3C33アンプとVT-62アンプは電圧チェックを省き、目視チェックのみでいきなり電源を投入した。
どちらも半導体を一切使用していない。抵抗とコンデンサー、真空管とトランスだけで組んでいる。
回路にはガラスと金属、絶縁体意外はないから、経年劣化の恐れはないと推測したからだ。
イコライザーアンプではケースを開け、電圧をチェックした。心配したのはダイオードだった。
心臓部は金属とシリコンだが、それを包んでいるのが合成樹脂たから心配したわけだ。
この 45 アンプは出力段のマイナス電源にダイオード使っているが、異常は無かった。
ダイオードに経年劣化の心配が無いのなら、残る4台の内3台は現役バリバリの可能性大だろう。
最後の一台は改良中、中途で放置状態になったので、まずその作業を終えてからチェックの予定。
音出しチェック
小編成の音楽を聴くには最適かもしれない。トランスドライブのVT-62アンプに比べると、こちらは通常のCR
結合のためか、楽器の分離が良い印象で、奥行きも感じられる。
小編成向きとは書いたが、オーケストラがダメと言うわけではない。東京の住宅事情を考えたとき、年がら年中
コンサートホールS席の音量を出すわけには行かない。だから実用上、最大出力1.5Wで十分と言えると思う。
このことは、最大出力2WのVT-62アンプ、その他多くののシングルアンプに言えることだが。
考えられる改良点
1.62アンプ同様、入力直後の普及品ボリュームを、アルプスのデテントボリュームに換装。
2.小型電源トランスを追加、6.3VフィラメントのVT-52を使用可能にする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6CA7 純五極管接続 プッシュプルアンプ 状態:異状無し
回路構成概略
初段 UY-76
2段 UZ-42 三極管接続
出力段 UX-45 シングル(交流点火・固定バイアス)
OPT TANGO FW20S
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管以外を外し、真空管ソケットで測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター及びフィラメント電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
BIAS調節ツマミを回して 45 のプレート電流を35mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
3C33アンプとVT-62アンプは電圧チェックを省き、目視チェックのみでいきなり電源を投入した。
どちらも半導体を一切使用していない。抵抗とコンデンサー、真空管とトランスだけで組んでいる。
回路にはガラスと金属、絶縁体意外はないから、経年劣化の恐れはないと推測したからだ。
イコライザーアンプではケースを開け、電圧をチェックした。心配したのはダイオードだった。
心臓部は金属とシリコンだが、それを包んでいるのが合成樹脂たから心配したわけだ。
この 45 アンプは出力段のマイナス電源にダイオード使っているが、異常は無かった。
ダイオードに経年劣化の心配が無いのなら、残る4台の内3台は現役バリバリの可能性大だろう。
最後の一台は改良中、中途で放置状態になったので、まずその作業を終えてからチェックの予定。
音出しチェック
小編成の音楽を聴くには最適かもしれない。トランスドライブのVT-62アンプに比べると、こちらは通常のCR
結合のためか、楽器の分離が良い印象で、奥行きも感じられる。
小編成向きとは書いたが、オーケストラがダメと言うわけではない。東京の住宅事情を考えたとき、年がら年中
コンサートホールS席の音量を出すわけには行かない。だから実用上、最大出力1.5Wで十分と言えると思う。
このことは、最大出力2WのVT-62アンプ、その他多くののシングルアンプに言えることだが。
考えられる改良点
1.62アンプ同様、入力直後の普及品ボリュームを、アルプスのデテントボリュームに換装。
2.小型電源トランスを追加、6.3VフィラメントのVT-52を使用可能にする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6CA7 純五極管接続 プッシュプルアンプ 状態:異状無し
 回路構成概略
初段 14F7
2段 14AF7 ミュラード型位相反転
出力段 6L6 プッシュプル(固定バイアス・純五極管接続)
VR-150 6267×2 6AS7×2 にてプレート用、スクリーングリッド用、定電圧電源×2
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350V SG電圧 270V にセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を100mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
このアンプのコンセプトは「5極管の音は本当に悪いのか?」を確かめること。
6L6や6CA4などの真空管を純五極管接続として、メーカー指定通りの条件を与え、その音を確かめる。
プレートとスクリーングリッドに供給する電源は、それぞれ独立した定電圧電源としてみた。
出力段BIAS調整、DCバランス、B電源電圧、SG電源電圧を可変抵抗で調節可能である。
だから安否確認テストは簡単に済み、出力管は多種のものが試せる、実験機的性格のアンプである。
音出しチェック
このパワーアンプで初めて入力直後の可変抵抗に、アルプス電気のデテントボリュームを使った。
だからガリオームの心配は無く、可変抵抗によるノイズは皆無だった。
残念ながら「5極管の音は本当に悪いのか?」については分からない。本気でテストしたのは30年前だ。
記憶では、無帰還ではややキンキンした音に感じたと思う。この状態だとこのアンプは高感度過ぎて、
音量ボリュームの常用位置が、時計の八時付近になってしまう。だから音質改善のためというより、
感度調節のために、OPT二次側から初段のカソードへ、6だったか12dB負帰還をかけて完成させた。
その状態できいているからかも知れないが、今聴いても三極管との音質の違いなど分からない。
とにかく良い音だ。平日の昼間、コンサートホールS席の音量でブルックナーのシンフォニーを流す。
退職前は絶対にできなかったことだ。出力管に何を使うか、B電圧、BIASをどうするかにより変化するが、
最大出力15~20Wクラスのアンプだから安定感が違う。
考えられる改良点
1.出力段にカソードフィードバックをかけてみる。(現時点でその必要は感じないが)
2.三極管6B4Gを刺したときのため、ヒーター配線にハムバランサーを追加。(内部を見ないと分からないが)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PX25 または AT-20 シングルアンプ 状態:異状無し
回路構成概略
初段 14F7
2段 14AF7 ミュラード型位相反転
出力段 6L6 プッシュプル(固定バイアス・純五極管接続)
VR-150 6267×2 6AS7×2 にてプレート用、スクリーングリッド用、定電圧電源×2
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350V SG電圧 270V にセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を100mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
このアンプのコンセプトは「5極管の音は本当に悪いのか?」を確かめること。
6L6や6CA4などの真空管を純五極管接続として、メーカー指定通りの条件を与え、その音を確かめる。
プレートとスクリーングリッドに供給する電源は、それぞれ独立した定電圧電源としてみた。
出力段BIAS調整、DCバランス、B電源電圧、SG電源電圧を可変抵抗で調節可能である。
だから安否確認テストは簡単に済み、出力管は多種のものが試せる、実験機的性格のアンプである。
音出しチェック
このパワーアンプで初めて入力直後の可変抵抗に、アルプス電気のデテントボリュームを使った。
だからガリオームの心配は無く、可変抵抗によるノイズは皆無だった。
残念ながら「5極管の音は本当に悪いのか?」については分からない。本気でテストしたのは30年前だ。
記憶では、無帰還ではややキンキンした音に感じたと思う。この状態だとこのアンプは高感度過ぎて、
音量ボリュームの常用位置が、時計の八時付近になってしまう。だから音質改善のためというより、
感度調節のために、OPT二次側から初段のカソードへ、6だったか12dB負帰還をかけて完成させた。
その状態できいているからかも知れないが、今聴いても三極管との音質の違いなど分からない。
とにかく良い音だ。平日の昼間、コンサートホールS席の音量でブルックナーのシンフォニーを流す。
退職前は絶対にできなかったことだ。出力管に何を使うか、B電圧、BIASをどうするかにより変化するが、
最大出力15~20Wクラスのアンプだから安定感が違う。
考えられる改良点
1.出力段にカソードフィードバックをかけてみる。(現時点でその必要は感じないが)
2.三極管6B4Gを刺したときのため、ヒーター配線にハムバランサーを追加。(内部を見ないと分からないが)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PX25 または AT-20 シングルアンプ 状態:異状無し
 回路構成概略
初段 6SN7 SRPP
2段 6SN7 SRPP
出力段 PX25 シングル(固定バイアス)
VR-150 6267 6AS7×2 にて定電圧電源
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350Vにセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を90mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
定電圧電源を使う必要は無いのだろうが、出力管が何であってもツマミひとつで対応できるのが便利だ。
と言っても、ヨーロッパ系のUFソケットなのと、フィラメント電圧が4Vと6.3Vの二択なので、
実際にはそれほど幅が広いとは言えない。UXソケットなら出力管の選択肢は大きく広がるが・・・。
音出しチェック
このパワーアンプも、アルプス電気のデテントボリュームを使っていから快適だ。
再生音の方は、45アンプと同じ傾向。分離が良く澄んだ空気を感じさせるように思う。
ただし、こちらの方が最大出力が大きいから、大音量時の安定感はややまさっている。
考えられる改良点
1.ソケットをUXに変更。(2.5V電源を加えれば 45 や 2A3 も使える。)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6B4G UL接続 プッシュプルアンプ 状態:整流管の交換が必要
回路構成概略
初段 6SN7 SRPP
2段 6SN7 SRPP
出力段 PX25 シングル(固定バイアス)
VR-150 6267 6AS7×2 にて定電圧電源
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350Vにセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を90mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
定電圧電源を使う必要は無いのだろうが、出力管が何であってもツマミひとつで対応できるのが便利だ。
と言っても、ヨーロッパ系のUFソケットなのと、フィラメント電圧が4Vと6.3Vの二択なので、
実際にはそれほど幅が広いとは言えない。UXソケットなら出力管の選択肢は大きく広がるが・・・。
音出しチェック
このパワーアンプも、アルプス電気のデテントボリュームを使っていから快適だ。
再生音の方は、45アンプと同じ傾向。分離が良く澄んだ空気を感じさせるように思う。
ただし、こちらの方が最大出力が大きいから、大音量時の安定感はややまさっている。
考えられる改良点
1.ソケットをUXに変更。(2.5V電源を加えれば 45 や 2A3 も使える。)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6B4G UL接続 プッシュプルアンプ 状態:整流管の交換が必要
 回路構成概略
初段 6SN7
2段 6SN7
インプットトランス
出力段 6L6GC プッシュプル(固定バイアス・UL接続)
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管意外の真空管を外し測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を120mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
作業途中でトラブル発生、電源off チェック中断。
回路構成概略
初段 6SN7
2段 6SN7
インプットトランス
出力段 6L6GC プッシュプル(固定バイアス・UL接続)
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管意外の真空管を外し測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を120mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
作業途中でトラブル発生、電源off チェック中断。
 写真を撮っていると、パパッと整流管が白く輝き、電流計の針が下がっていく。
もう一度整流管を見ると、片側のプレートが赤熱している。5AR4が死んだ。
急いで電源を切った。
5~6本買ったはずの5AR4のスペアが見当たらないので、テストの続行は補充してからになる。
だが、整流管の5AR4を交換すればこのアンプも正常に動作すると思った。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ここまでの安否確認が済んだとき、五月もあと少しで終わる頃になっていた。まず
トーンアンプの修理だ。そのあと未チェックの2台のアンプを修理したい。しかし、
改めて考えてみると、プロ用、医療用、軍用の機器やパーツは凄い。自作したアンプ
達9台のうち6台がそのまま動いた。残る3台も修理可能だ。
少なくてもこの25年間、一切触っていない。完全に放置状態だった。中でも一番
古い VT-62 アンプは、完成から40年間無故障である。シャーシを開けたこ
とは一度もない。何十年も放置したのに、いまも以前と変わらずに期待に応えてくれ
た。そのようなものを、2020年現在、手に入れることは出きるのだろうか?
親ページに戻る その1へ<-その2<-その3
写真を撮っていると、パパッと整流管が白く輝き、電流計の針が下がっていく。
もう一度整流管を見ると、片側のプレートが赤熱している。5AR4が死んだ。
急いで電源を切った。
5~6本買ったはずの5AR4のスペアが見当たらないので、テストの続行は補充してからになる。
だが、整流管の5AR4を交換すればこのアンプも正常に動作すると思った。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ここまでの安否確認が済んだとき、五月もあと少しで終わる頃になっていた。まず
トーンアンプの修理だ。そのあと未チェックの2台のアンプを修理したい。しかし、
改めて考えてみると、プロ用、医療用、軍用の機器やパーツは凄い。自作したアンプ
達9台のうち6台がそのまま動いた。残る3台も修理可能だ。
少なくてもこの25年間、一切触っていない。完全に放置状態だった。中でも一番
古い VT-62 アンプは、完成から40年間無故障である。シャーシを開けたこ
とは一度もない。何十年も放置したのに、いまも以前と変わらずに期待に応えてくれ
た。そのようなものを、2020年現在、手に入れることは出きるのだろうか?
親ページに戻る その1へ<-その2<-その3


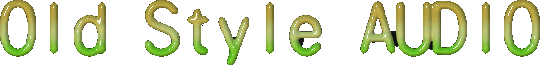
 回路構成概略
初段 UY-76
2段 UZ-42 三極管接続
出力段 UX-45 シングル(交流点火・固定バイアス)
OPT TANGO FW20S
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管以外を外し、真空管ソケットで測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター及びフィラメント電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
BIAS調節ツマミを回して 45 のプレート電流を35mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
3C33アンプとVT-62アンプは電圧チェックを省き、目視チェックのみでいきなり電源を投入した。
どちらも半導体を一切使用していない。抵抗とコンデンサー、真空管とトランスだけで組んでいる。
回路にはガラスと金属、絶縁体意外はないから、経年劣化の恐れはないと推測したからだ。
イコライザーアンプではケースを開け、電圧をチェックした。心配したのはダイオードだった。
心臓部は金属とシリコンだが、それを包んでいるのが合成樹脂たから心配したわけだ。
この 45 アンプは出力段のマイナス電源にダイオード使っているが、異常は無かった。
ダイオードに経年劣化の心配が無いのなら、残る4台の内3台は現役バリバリの可能性大だろう。
最後の一台は改良中、中途で放置状態になったので、まずその作業を終えてからチェックの予定。
音出しチェック
小編成の音楽を聴くには最適かもしれない。トランスドライブのVT-62アンプに比べると、こちらは通常のCR
結合のためか、楽器の分離が良い印象で、奥行きも感じられる。
小編成向きとは書いたが、オーケストラがダメと言うわけではない。東京の住宅事情を考えたとき、年がら年中
コンサートホールS席の音量を出すわけには行かない。だから実用上、最大出力1.5Wで十分と言えると思う。
このことは、最大出力2WのVT-62アンプ、その他多くののシングルアンプに言えることだが。
考えられる改良点
1.62アンプ同様、入力直後の普及品ボリュームを、アルプスのデテントボリュームに換装。
2.小型電源トランスを追加、6.3VフィラメントのVT-52を使用可能にする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6CA7 純五極管接続 プッシュプルアンプ 状態:異状無し
回路構成概略
初段 UY-76
2段 UZ-42 三極管接続
出力段 UX-45 シングル(交流点火・固定バイアス)
OPT TANGO FW20S
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管以外を外し、真空管ソケットで測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター及びフィラメント電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
BIAS調節ツマミを回して 45 のプレート電流を35mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
3C33アンプとVT-62アンプは電圧チェックを省き、目視チェックのみでいきなり電源を投入した。
どちらも半導体を一切使用していない。抵抗とコンデンサー、真空管とトランスだけで組んでいる。
回路にはガラスと金属、絶縁体意外はないから、経年劣化の恐れはないと推測したからだ。
イコライザーアンプではケースを開け、電圧をチェックした。心配したのはダイオードだった。
心臓部は金属とシリコンだが、それを包んでいるのが合成樹脂たから心配したわけだ。
この 45 アンプは出力段のマイナス電源にダイオード使っているが、異常は無かった。
ダイオードに経年劣化の心配が無いのなら、残る4台の内3台は現役バリバリの可能性大だろう。
最後の一台は改良中、中途で放置状態になったので、まずその作業を終えてからチェックの予定。
音出しチェック
小編成の音楽を聴くには最適かもしれない。トランスドライブのVT-62アンプに比べると、こちらは通常のCR
結合のためか、楽器の分離が良い印象で、奥行きも感じられる。
小編成向きとは書いたが、オーケストラがダメと言うわけではない。東京の住宅事情を考えたとき、年がら年中
コンサートホールS席の音量を出すわけには行かない。だから実用上、最大出力1.5Wで十分と言えると思う。
このことは、最大出力2WのVT-62アンプ、その他多くののシングルアンプに言えることだが。
考えられる改良点
1.62アンプ同様、入力直後の普及品ボリュームを、アルプスのデテントボリュームに換装。
2.小型電源トランスを追加、6.3VフィラメントのVT-52を使用可能にする。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6CA7 純五極管接続 プッシュプルアンプ 状態:異状無し
 回路構成概略
初段 14F7
2段 14AF7 ミュラード型位相反転
出力段 6L6 プッシュプル(固定バイアス・純五極管接続)
VR-150 6267×2 6AS7×2 にてプレート用、スクリーングリッド用、定電圧電源×2
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350V SG電圧 270V にセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を100mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
このアンプのコンセプトは「5極管の音は本当に悪いのか?」を確かめること。
6L6や6CA4などの真空管を純五極管接続として、メーカー指定通りの条件を与え、その音を確かめる。
プレートとスクリーングリッドに供給する電源は、それぞれ独立した定電圧電源としてみた。
出力段BIAS調整、DCバランス、B電源電圧、SG電源電圧を可変抵抗で調節可能である。
だから安否確認テストは簡単に済み、出力管は多種のものが試せる、実験機的性格のアンプである。
音出しチェック
このパワーアンプで初めて入力直後の可変抵抗に、アルプス電気のデテントボリュームを使った。
だからガリオームの心配は無く、可変抵抗によるノイズは皆無だった。
残念ながら「5極管の音は本当に悪いのか?」については分からない。本気でテストしたのは30年前だ。
記憶では、無帰還ではややキンキンした音に感じたと思う。この状態だとこのアンプは高感度過ぎて、
音量ボリュームの常用位置が、時計の八時付近になってしまう。だから音質改善のためというより、
感度調節のために、OPT二次側から初段のカソードへ、6だったか12dB負帰還をかけて完成させた。
その状態できいているからかも知れないが、今聴いても三極管との音質の違いなど分からない。
とにかく良い音だ。平日の昼間、コンサートホールS席の音量でブルックナーのシンフォニーを流す。
退職前は絶対にできなかったことだ。出力管に何を使うか、B電圧、BIASをどうするかにより変化するが、
最大出力15~20Wクラスのアンプだから安定感が違う。
考えられる改良点
1.出力段にカソードフィードバックをかけてみる。(現時点でその必要は感じないが)
2.三極管6B4Gを刺したときのため、ヒーター配線にハムバランサーを追加。(内部を見ないと分からないが)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PX25 または AT-20 シングルアンプ 状態:異状無し
回路構成概略
初段 14F7
2段 14AF7 ミュラード型位相反転
出力段 6L6 プッシュプル(固定バイアス・純五極管接続)
VR-150 6267×2 6AS7×2 にてプレート用、スクリーングリッド用、定電圧電源×2
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350V SG電圧 270V にセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を100mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
このアンプのコンセプトは「5極管の音は本当に悪いのか?」を確かめること。
6L6や6CA4などの真空管を純五極管接続として、メーカー指定通りの条件を与え、その音を確かめる。
プレートとスクリーングリッドに供給する電源は、それぞれ独立した定電圧電源としてみた。
出力段BIAS調整、DCバランス、B電源電圧、SG電源電圧を可変抵抗で調節可能である。
だから安否確認テストは簡単に済み、出力管は多種のものが試せる、実験機的性格のアンプである。
音出しチェック
このパワーアンプで初めて入力直後の可変抵抗に、アルプス電気のデテントボリュームを使った。
だからガリオームの心配は無く、可変抵抗によるノイズは皆無だった。
残念ながら「5極管の音は本当に悪いのか?」については分からない。本気でテストしたのは30年前だ。
記憶では、無帰還ではややキンキンした音に感じたと思う。この状態だとこのアンプは高感度過ぎて、
音量ボリュームの常用位置が、時計の八時付近になってしまう。だから音質改善のためというより、
感度調節のために、OPT二次側から初段のカソードへ、6だったか12dB負帰還をかけて完成させた。
その状態できいているからかも知れないが、今聴いても三極管との音質の違いなど分からない。
とにかく良い音だ。平日の昼間、コンサートホールS席の音量でブルックナーのシンフォニーを流す。
退職前は絶対にできなかったことだ。出力管に何を使うか、B電圧、BIASをどうするかにより変化するが、
最大出力15~20Wクラスのアンプだから安定感が違う。
考えられる改良点
1.出力段にカソードフィードバックをかけてみる。(現時点でその必要は感じないが)
2.三極管6B4Gを刺したときのため、ヒーター配線にハムバランサーを追加。(内部を見ないと分からないが)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PX25 または AT-20 シングルアンプ 状態:異状無し
 回路構成概略
初段 6SN7 SRPP
2段 6SN7 SRPP
出力段 PX25 シングル(固定バイアス)
VR-150 6267 6AS7×2 にて定電圧電源
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350Vにセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を90mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
定電圧電源を使う必要は無いのだろうが、出力管が何であってもツマミひとつで対応できるのが便利だ。
と言っても、ヨーロッパ系のUFソケットなのと、フィラメント電圧が4Vと6.3Vの二択なので、
実際にはそれほど幅が広いとは言えない。UXソケットなら出力管の選択肢は大きく広がるが・・・。
音出しチェック
このパワーアンプも、アルプス電気のデテントボリュームを使っていから快適だ。
再生音の方は、45アンプと同じ傾向。分離が良く澄んだ空気を感じさせるように思う。
ただし、こちらの方が最大出力が大きいから、大音量時の安定感はややまさっている。
考えられる改良点
1.ソケットをUXに変更。(2.5V電源を加えれば 45 や 2A3 も使える。)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6B4G UL接続 プッシュプルアンプ 状態:整流管の交換が必要
回路構成概略
初段 6SN7 SRPP
2段 6SN7 SRPP
出力段 PX25 シングル(固定バイアス)
VR-150 6267 6AS7×2 にて定電圧電源
電圧チェック
シャーシは開けずに、すべての真空管を外し測定。
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 B電圧 350Vにセット。
BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を90mAにセット。
ハムバランサーの可変抵抗を調節、ハム音最小の位置にセット。
以上で音出しチェックの準備完了。
定電圧電源を使う必要は無いのだろうが、出力管が何であってもツマミひとつで対応できるのが便利だ。
と言っても、ヨーロッパ系のUFソケットなのと、フィラメント電圧が4Vと6.3Vの二択なので、
実際にはそれほど幅が広いとは言えない。UXソケットなら出力管の選択肢は大きく広がるが・・・。
音出しチェック
このパワーアンプも、アルプス電気のデテントボリュームを使っていから快適だ。
再生音の方は、45アンプと同じ傾向。分離が良く澄んだ空気を感じさせるように思う。
ただし、こちらの方が最大出力が大きいから、大音量時の安定感はややまさっている。
考えられる改良点
1.ソケットをUXに変更。(2.5V電源を加えれば 45 や 2A3 も使える。)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6L6 または 6B4G UL接続 プッシュプルアンプ 状態:整流管の交換が必要
 回路構成概略
初段 6SN7
2段 6SN7
インプットトランス
出力段 6L6GC プッシュプル(固定バイアス・UL接続)
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管意外の真空管を外し測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を120mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
作業途中でトラブル発生、電源off チェック中断。
回路構成概略
初段 6SN7
2段 6SN7
インプットトランス
出力段 6L6GC プッシュプル(固定バイアス・UL接続)
電圧チェック
シャーシは開けずに、整流管意外の真空管を外し測定。
B電源・・・異状無し
ヒーター電源・・・異状無し
出力段BIAS負電源・・・異状無し
電源offの後、各真空管をセット、BIASを最大値にセットして電源投入。
出力段 BIAS調節ツマミを回してのプレート電流を120mAにセット。
DCバランスの可変抵抗を調節、0位置にセット。
作業途中でトラブル発生、電源off チェック中断。
 写真を撮っていると、パパッと整流管が白く輝き、電流計の針が下がっていく。
もう一度整流管を見ると、片側のプレートが赤熱している。5AR4が死んだ。
急いで電源を切った。
5~6本買ったはずの5AR4のスペアが見当たらないので、テストの続行は補充してからになる。
だが、整流管の5AR4を交換すればこのアンプも正常に動作すると思った。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ここまでの安否確認が済んだとき、五月もあと少しで終わる頃になっていた。まず
トーンアンプの修理だ。そのあと未チェックの2台のアンプを修理したい。しかし、
改めて考えてみると、プロ用、医療用、軍用の機器やパーツは凄い。自作したアンプ
達9台のうち6台がそのまま動いた。残る3台も修理可能だ。
少なくてもこの25年間、一切触っていない。完全に放置状態だった。中でも一番
古い VT-62 アンプは、完成から40年間無故障である。シャーシを開けたこ
とは一度もない。何十年も放置したのに、いまも以前と変わらずに期待に応えてくれ
た。そのようなものを、2020年現在、手に入れることは出きるのだろうか?
親ページに戻る その1へ<-その2<-その3
写真を撮っていると、パパッと整流管が白く輝き、電流計の針が下がっていく。
もう一度整流管を見ると、片側のプレートが赤熱している。5AR4が死んだ。
急いで電源を切った。
5~6本買ったはずの5AR4のスペアが見当たらないので、テストの続行は補充してからになる。
だが、整流管の5AR4を交換すればこのアンプも正常に動作すると思った。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ここまでの安否確認が済んだとき、五月もあと少しで終わる頃になっていた。まず
トーンアンプの修理だ。そのあと未チェックの2台のアンプを修理したい。しかし、
改めて考えてみると、プロ用、医療用、軍用の機器やパーツは凄い。自作したアンプ
達9台のうち6台がそのまま動いた。残る3台も修理可能だ。
少なくてもこの25年間、一切触っていない。完全に放置状態だった。中でも一番
古い VT-62 アンプは、完成から40年間無故障である。シャーシを開けたこ
とは一度もない。何十年も放置したのに、いまも以前と変わらずに期待に応えてくれ
た。そのようなものを、2020年現在、手に入れることは出きるのだろうか?
親ページに戻る その1へ<-その2<-その3